「純文学」と聞くと、ちょっと難しそうなイメージがありませんか?
登場人物の心情や風景描写が繊細で、物語の展開もスピーディーではない。だからこそ、普段あまり本を読まない人にとっては、「話が進まなくて退屈」「何を言いたいのかよくわからない」と思ってしまうかもしれません。
でも、純文学には純文学ならではの「味わい方」があるのです。
今回は、読書初心者さんが純文学をもっと楽しめるように、「行間を読む」と「比喩表現を楽しむ」という2つの視点から、そのコツを解説していきます。
行間を読む
「行間を読む」という言葉、聞いたことはありますか?
これは、文章に直接書かれていない情報を読み取ることを意味します。例えば、登場人物の表情や仕草の描写があるとき、その背後にある感情や意図を想像してみる。そうすることで、物語がより奥深く、面白くなります。
「大きなニキビ」は青年性を表す?
たとえば、芥川龍之介の『羅生門』を例に考えてみましょう。
右の頬に出来た、大きな面皰
芥川龍之介「羅生門」より
を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺めていた。
この作品の主人公は「頬に大きなニキビのある男」です。一見、なんてことのない外見の描写ですが、一歩踏み込んで「なぜわざわざニキビについて書かれているのか?」を考えてみましょう。
ニキビは青年性の象徴であり、彼が「まだ若く、迷いの多い時期にいる」ことを示しているとも解釈できます。
そして、この作品の終盤では、以下のように「ニキビ」が描かれます。
そうして、一足前へ出ると、不意に右の手を面皰
芥川龍之介「羅生門」より
から離して、老婆の襟上
をつかみながら、噛みつくようにこう云った。
作中で人生の岐路に立たされた主人公が「ニキビから手を離した」ことは「青年性を手放した」という解釈につながります。
このように、文章に明確には書かれていなくても、「これは何かを意味しているのでは?」と考えることで、作品がより面白く感じられるのです。
直接的な表現を避ける美しさ
また、文学作品では「言葉を濁す」ことがよくあります。例えば、登場人物の気持ちを「彼は悲しかった」とストレートに書くのではなく「彼は窓の外をじっと見つめた」と描写することで、読者にその感情を想像させるのです。
文章の裏に隠された意味を考えること。それが、純文学をより深く味わうための第一歩です。
独特な比喩表現を楽しむ
比喩表現とは、あるものを別のものになぞらえて表現すること。文学作品はこの「比喩表現の豊かさ」を味わえるようになると、格段に読書の楽しさがアップします。
比喩表現を使えばできること
では、試しに事実だけを用いて風景を描いてみましょう。
右には3本の高い木があり、左には猫がいる。空は赤く染まっている。僕は怒り心頭していた。
こちらは、シンプルなレポート調の文章です。事実だけを述べているため、「怒り心頭していた」という割には、落ち着いた印象を受ける文章ですね。
それでは、この文章に比喩表現を用いて「激怒しているんだな」と思えるような心情を描いてみましょう。
3本の木は黒い槍のように天を突き、猫は沈む太陽を眺めながら、ゆっくりと前足を舐めている。空はまるで燃え上がる炎のように真っ赤に染まっていて、まさに僕の心の中を映しているようだった。
単なる風景の説明から一変して、途端に「夕闇の情景」や「燃え盛るような怒りの感情」が浮かび上がるような感じがしませんか?このように、比喩表現は情景だけでなく、登場人物の感情などの重要な情報を伝える役割を担っています。
また、作家ごとに比喩表現の癖があるので、そこに着目してみるのも楽しいのでおすすめです。
まとめ
純文学は「難しそう」と思われがちですが、ちょっとしたコツを掴めば、その魅力がどんどん見えてきます。
- 行間を読む:書かれていない部分に注目し、登場人物の感情や作者の意図を想像してみる。
- 比喩表現を楽しむ:独特な表現の面白さを味わい、文章の持つ奥深さを感じる。
最初は「よくわからないな」と思うかもしれません。でも、ちょっとした発見を積み重ねることで、純文学の世界はぐっと広がります。
ぜひ、自分なりの読み方を見つけながら、純文学を楽しんでみてください!
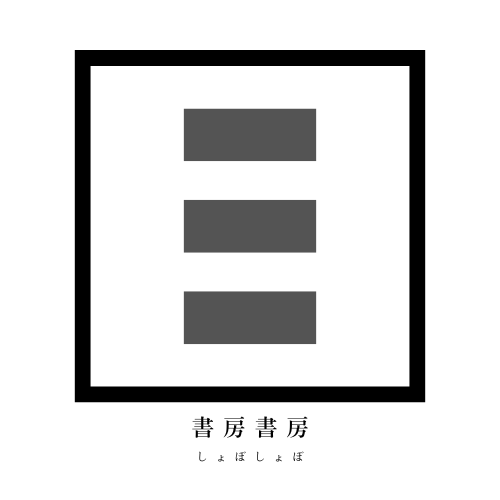
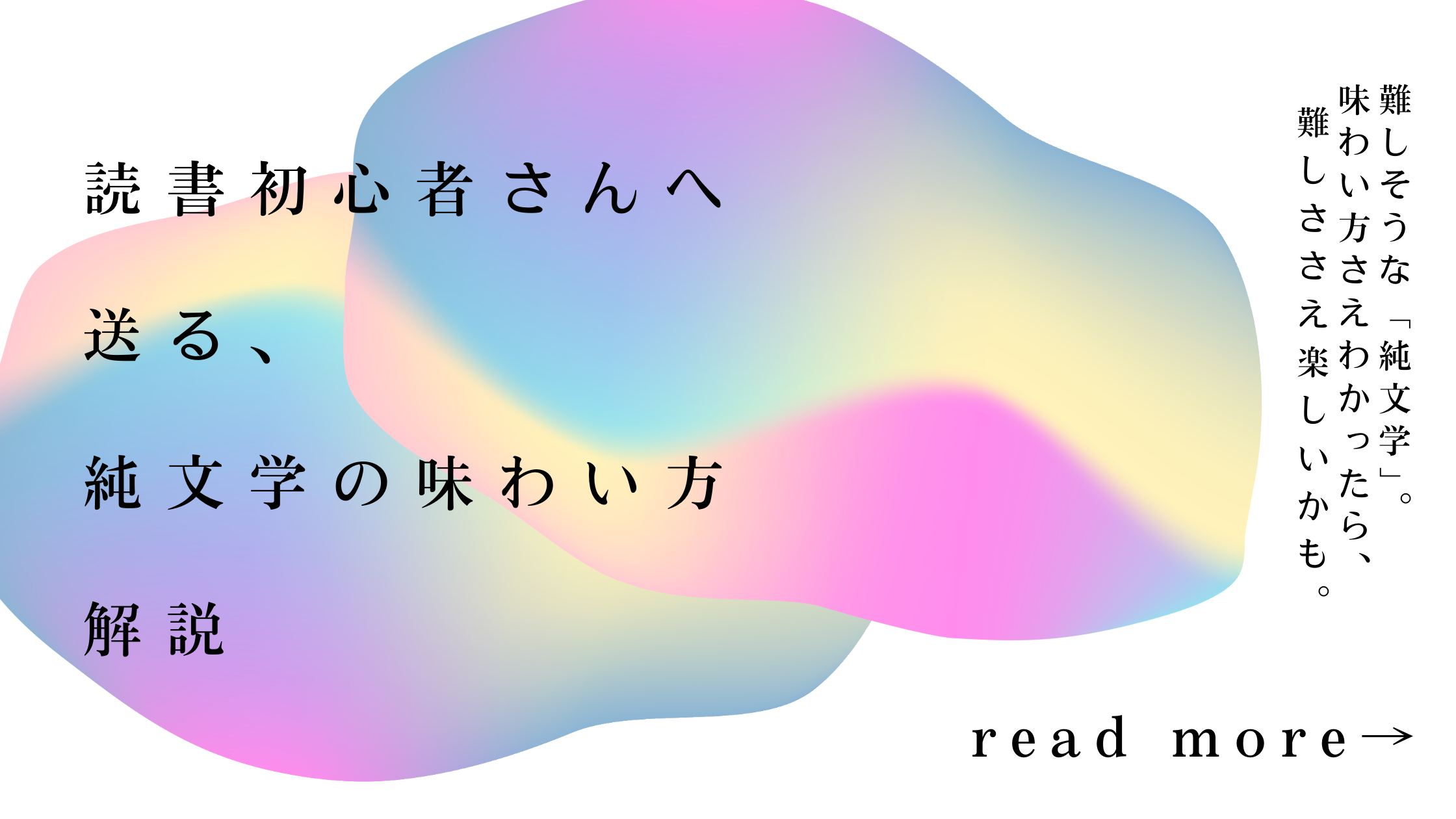
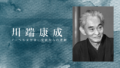

コメント